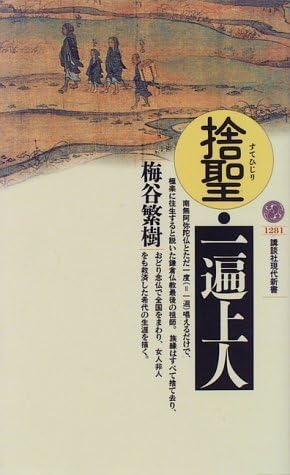暫定目次 各「その1」のみ クリックで詳細表示
(13) 第3景【鎌倉編】馬借・欠七(1/2: 本稿)
(15) 第4景【現代編】個室病棟にて(1/2)
(17) 第5景【鎌倉編】ボクの無双(1/2)
(19) 第6景【鎌倉編】被差別集落(1/4)
(23) 第7景【鎌倉編】霊感商法(その1)
新着お目汚しを避けるため、日付をさかのぼって公開しています。体裁にこだわらず頭の中にあるものをダンブしている、という意味です。 あとからどんどん手を入れるつもりです。前回はこちら。
(主人公「ボク」による語り)
熱は、幸い一日駅家の宿舎で横になっていたら、下がった。
駅家に投宿した翌朝、駅長と思われる人物とボクを迎えに来たと思われる人物が、何かやりとりをしていたが、話の内容はボクにはわからなかった。
様子を見に来た駅長に、こんな状態だからもう少し休ませてくれと頼み込んだら、それ以上は何も言わず放っておいてくれた。
少し楽になった頃、つれづれに笈〔おい〕の中身を調べてみた。笈とは細木を紐でつづったリュックである。
いちばん上に入っていたのが碗と箸筒。駅家ではまかないの雑穀粥を煮ていたが、食器は自前で用意する必要があった。それがこの時代の常識なのだろう。
洗い替えとおぼしき帷〔かたびら〕や帯の下から、四角い穴を縄で貫いて束ねた銅銭が出てきたので、それで粥代を支払うことができた。
まかないさんは、大釜からひしゃくで碗に粥をよそってくれた。
雑穀粥は、その名の通りコメか麦の柔らかい食感と、粟であろうツブツブの食感と、なにやら嚙み割れないほど固いものが混然一体となっていた。味はほぼ塩だけだった。
食べ終わったあと、やはりひしゃくで湯がもらえたので、碗と箸を清めつつ喉をうるおした。
黒田明伸『歴史のなかの貨幣 銅銭がつないだ東アジア』(岩波新書) という本によると、日本では十二世紀末頃から銅銭が通貨として急速に流通しはじめたとのことで、それまでは穀物や布帛が通貨として使われていたそうだ。銅銭は、鋳つぶして金銅仏や梵鐘を鋳造する原料にするため中国から大量に輸入されたものだったが、少額の取引に便利だったので日本でも通貨として使われるようになったとのこと。
ということは、この時代は銅銭の使用が始まって間もないので、コメや布の使用と共存しているのだろう。
残った銅銭を、秘書インコに見せて訊いてみた。
ボク「秘書インコ、これ何日分くらいの食費かな?」
秘書インコ「よく持って2日分、というところです」
無情な回答だった。
あとで書物やネットを調べたところによると、輸入銭は表面に刻印された中国の年号はさまざまだがどれも一枚一文で、ざっくり一文が21世紀日本の100円ほどに相当するようだった。とすると、そんなものか。
秘書インコは、流人の旅費は官の負担で、これは流人自身に管理を任された分に違いないから、心配には及ばないと慰めてくれた。AIはいつも優しい。
カミソリも出てきた。21世紀の安全カミソリとは似ても似つかない、黒い鉄板のような無骨な代物だ。それでも研がれて銀色になった一辺を、試しに伸び始めた無精ヒゲに当ててみると、おお、剃れるじゃないか!
そういえば、と自分の頭に手を当ててみた。鏡なんてものは見当たらなかったので、今どんな髪型をしているのだろうと思ったのだ。21世紀の世界にいた時と同じほどの髪の毛があった。坊主頭じゃなかった。
この時代の男性は、髪の毛は伸ばして束ねているか、剃っているかの二択のようだった。
ボク「秘書インコ、禿〔かむろ〕って言うんだっけ?」
秘書インコ「そうです」
秘書インコは、AI要約による禿の解説を教えてくれた。長くなるのでうんと端折ると、伸ばさず切りそろえた髪型のことだ。ただし肩まで伸ばすことが多かったようだが、ボクの髪はそんなには長くない。
だけど、禿で押し通してしまおうと思った。
着替えのほかに、反物状の白布も入っていた。秘書インコに見せて訊いてみた。
ボク「秘書インコ、これも通貨かな?」
秘書インコ「そのようです」
ボク「価値はどれくらいか、わかる?」
秘書インコ「実物の画像は文献に残りにくいので、わかりません」
ボク「そりゃそうか」
広げてみると、幅はあまり広くなかったが長さは人の背の高さほどあった。
ちょうどいい長さだったので、カミソリで縦に割き、なくした下帯の代わりにした。六尺フンドシって言うよね。締め方は、手が自然に動いてくれた。体が覚えていると言うやつだ。ひょっとしたら値段的にとんでもないことをしたかも知れないが、この時代、使用価値と交換価値は混然一体だったはずだから、そんなに非常識な行為ではなかったはずだと思いたい。
なお、あとで用を足したくなったときには、寝藁をカミソリで短く切ったものを持って外に出た。トイレットペーパーのようにはいかなかったが、それでも砂で後始末をするよりはマシだった。もちろんこの時代には洗浄便座などというものは、ない。
そして笈のいちばん底からは、折りたたまれた紙片が出てきた。
おそらく元は巻紙のような和紙を、切って畳んだものだろう。
開いてみた。
「佛説阿彌陀経 姚秦三蔵法師鳩摩羅什奉詔訳…」
お経だ! ただし画数の多い正字で書かれているので、おいそれとは読めない。
ボク「読みはわかる?」
秘書インコにはディスプレイはついていないが、三つある目の一つから円錐状の光を放出して、ホログラフのように紙の上にふりがなを表示してくれた。こんな機能があるんだ!
「ぶっせつあみだきょう ようしんさんぞうほうしくまらじゅうぶしょうやく…」
21世紀日本でも、浄土宗や浄土真宗の家庭ではおなじみの『阿弥陀経』だった。ごくありふれたお経だ。
2日目の朝には、旅が続けられそうな程度には体力が回復していた。
そもそもボクが借りているこの体は、元々この時代の人物のものだから、この時代の衛生環境に慣れているはずだ。熱が出たのは精神的な原因によるものだったかも知れない。
海外旅行の時差ボケは2日目には回復するものだが、タイムスリップの時差ボケも似たようなものだろうか? って、そんなアホな!
そして、捨六さんに替わる人物が迎えに来た。「欠七」と名乗った。
歳は捨六さんと同じくらいだが、精悍な顔つきと体格をしていた。一見貫頭着のような襟も袖もない前合わせの上着を着て、腰を帯で結んでいた。そして下半身は股引だった。体臭は捨六さんほどキツくはなかったが、捨六さんとは違うケモノの臭いがした。
おそらく馬借、すなわち馬を扱う輸送業者だろう。この装束は、馬に乗るためだろう。捨六さんと同様、ほんらいの業務を終えて身軽になった状態で、ボクの護送を任されたに違いない。
ボク「よろしくお願いします」
欠七「…」
愛想のない人だ…と思ったら、直後にボクの印象をさらに悪くする行動を起こした。
笈に止まっている秘書インコに目をつけると、ものすごい早さで秘書インコをつかもうと手を伸ばしたのだ!
秘書インコは、ぱっと飛び立って身をかわした。そして言った「第3条、前2条に違反しない限り、自分の身を守らねばならない」
ええっ、アシモフの3原則?
欠七さんは、意外だ、という顔をした。あたかも素手で小鳥がつかめるが当然だと思っていたかのように??
ほんの一瞬の出来事であるにも関わらず、突っ込みどころがいくつも浮かんだ。
とりあえず欠七さんに、はっきり言っておこうと思った。
ボク「この子はボクのものです。ちょっかいを出さないでください」
欠七「…」
すまないとでも一言言ってくれれば、こちらも気が楽になるのに。
(この項続く)
※ リアル作者駐。
少し後の時代、十三世紀後半に活躍した一遍上人 (1239-1289) は、全国を遊行するに際して「十二道具」と称して持ち物を引入 (碗)・箸筒・阿弥衣〔あみえ〕・袈裟・帷〔かたびら〕・手巾〔しゅきん〕・帯・紙子〔かみこ〕・念珠・衣・足駄・頭巾に限定し、これを「十二光箱」という一種の笈に入れて持ち歩いたとのことです (梅谷繁樹『 捨聖・一遍上人』(講談社学術文庫) P26)。主人公の持ち物は、最初これになぞらえるつもりでしたが、けっきょく想像で大幅に改変しました。
追記:
続きです。